
広告媒体としてフライヤー(チラシ)を利用している場合、「フライヤーの裏面には何を掲載すべき?」「フライヤーの裏面を効果的に使いたい」といったことでお悩みの方は多いのではないでしょうか。
節約効果の高い両面印刷ですが、表と裏の特性を知らずに利用していてはせっかくの宣伝効果も半減してしまう可能性があります。
本記事ではフライヤーの裏面に掲載したい情報、裏面デザインの手順やポイントについて解説いたします。
フライヤーの成果を感じられていないという方は、ぜひ参考にしてみてください。
【 目次 】
フライヤー(チラシ)の裏面が真の購買契機
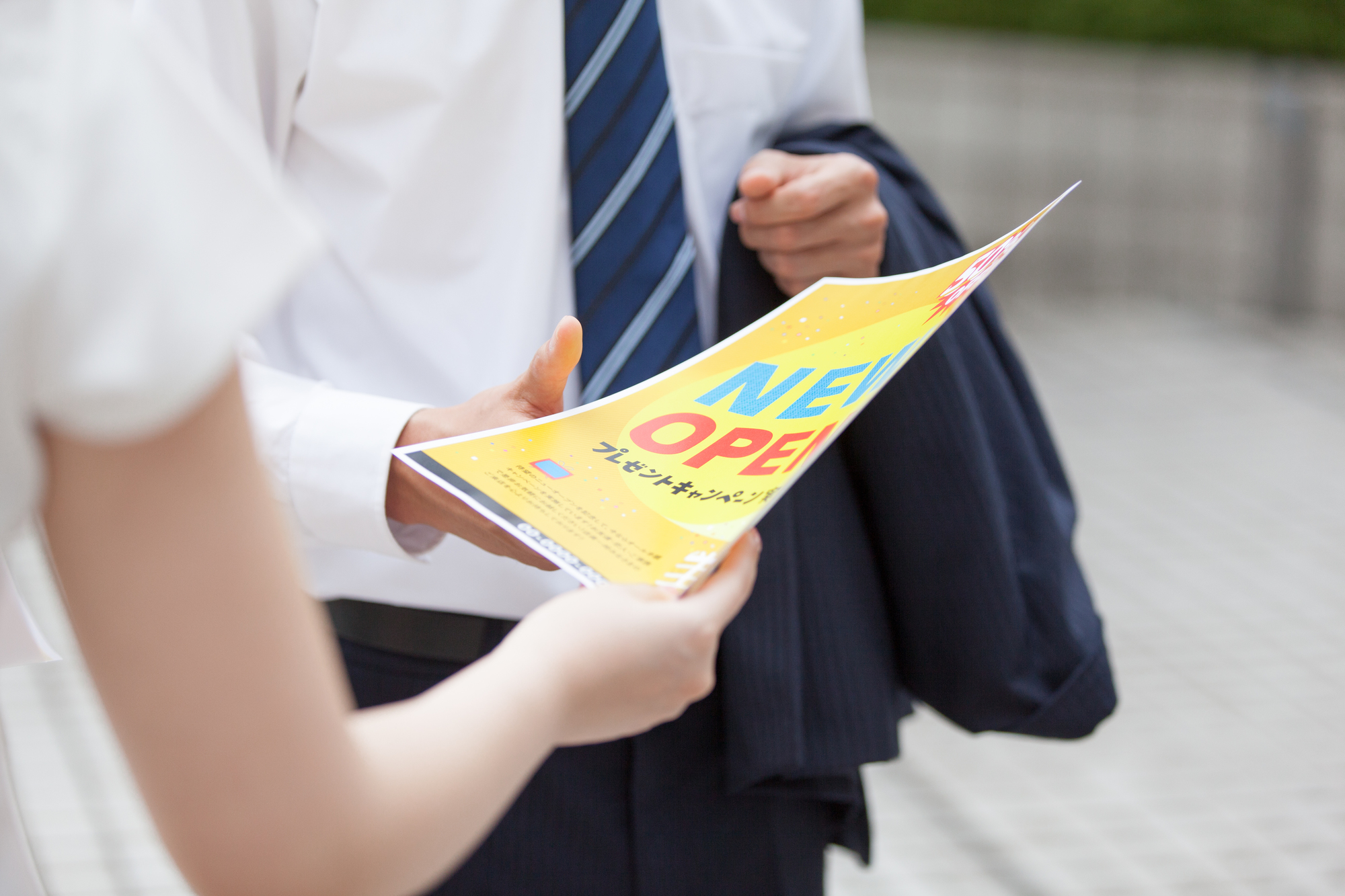
販促ツールのひとつとして利用されるフライヤーですが、表面と裏面それぞれの役割についてご存じでしょうか?
実は、フライヤーの裏面は真の購買契機と位置付けられるものです。
まずはその理由について解説いたします。
フライヤーの裏面が顧客のアクションへつながる
フライヤーの裏面には、表面に掲載できなかった情報が記載されます。
その内容は商品やサービスに関する詳しい情報、加えて店舗へのアクセス情報などが一般的です。
フライヤーを手に取った方は裏面の情報を参照して、商品の利用を具体的にイメージしたり店舗への来店を検討したりします。
つまりフライヤーの裏面が、顧客の直接的なアクションを誘発するきっかけとなるのです。
フライヤーの表面が持つ役割は手に取ってもらうこと
フライヤーの表面に求められることは、目立つデザインでとりあえず手に取ってもらうこと、最も伝えたい情報を最短で読み手の視野に入れることです。
商品が持つ大きな特徴をアピールして、少しでも興味を持ってもらうという点に表面の役割があります。
表面を見ただけでは読み手の具体的なアクションは起きないため、真の購買契機は裏面にあるということです。
フライヤーの裏面に掲載したいレイアウト情報
フライヤーの裏面に掲載することになるのは、表面でのスペースを割けなかった情報になります。
主に以下のような内容が記載されることになります。
- 詳しい商品情報
- 商品に関するデータ
- 購入した方の声やよくある質問
- アクセス情報
詳しい商品情報
フライヤーの裏面に多いのは、2番目以降におすすめしたい商品やサービスの情報です。
表面に記載された商品に興味を持った読み手は、ほかの商品についても知りたいと思う可能性があります。
裏面の情報を読んでさらに興味を深めてもらえば、具体的な購買アクションへとつなげることも可能です。
商品に関するデータ
商品に関するデータも裏面に記載されることが多々あります。
このデータとは商品のスペックのみならず、魅力を客観的に示した人気ランキングや商品が持つ効能・効果などの数値も含みます。
信用度の高いデータを提示して読み手を安心させることで、商品の購入への期待感を高めることができます。
細かい数字は興味を抱いていないと読んでもらえないため、裏面に記載すべき内容といえるでしょう。
購入した方の声やよくある質問
人は使ったことのない商品やサービスに関して、さまざまな疑問を抱きます。
その疑問を解消できれば、購買行動に移ってくれる可能性が高まります。
しかし、その疑問を解決しようと主体的に動くケースは少ないといえます。
そこで購入した方の声やよくある質問を裏面に掲載しておくことで、読み手の手間をかけずに疑問を解決してもらうのです。
「購入した方の声」についても読み手が実際に購入したときの効果がイメージしやすくなり、購買行動につながりやすいといわれています。
「よくある質問」の形式も顧客の8割程度が悩みを解決できるといわれていますので、裏面に記載すべき有用な情報です。
アクセス情報
アクセス情報はフライヤーの裏面に必須の情報といえます。
なぜなら疑問を解決するときと同様に、読み手自らアクセス情報を調べるケースは少ないからです。
店舗へ来店してくれる可能性があるのにアクセス情報がないことで、せっかくのチャンスを失ってしまうおそれもあります。
フライヤーの裏面には、アクセス情報を記載するようにしましょう。
フライヤー裏面にも使えるレイアウト決定までの手順
フライヤーの裏面に記載すべき情報がわかっていても、レイアウトに関して自信がないという方もいるでしょう。
そこでここからはフライヤー裏面にも使えるレイアウト決定までの手順と題して、踏むべき正しいステップについて解説いたします。
手順1:情報の優先順位を決める
まずは裏面に記載したい情報を抽出して、関連性のある情報同士をくっつけます。
分類後の数はチラシサイズにもよりますが、A4サイズで4つぐらいのグループが適当です。
その次はまとめた情報に対して、それぞれの優先度を決めていきましょう。
4つのグループであるなら最も伝えたい情報を①とし、最後に伝えたい情報を④とします。
手順2:ラフなレイアウトを決定する
次に手書きのブロック状で構わないのでチラシサイズをイメージした四角形の中に、それぞれの情報をラフに配置していきます。
スペースのサイズについては、先ほど決めた優先度を指標にして決定していきましょう。
すなわち優先度①の情報が大きな領域を占め、番号が下がっていくほどスペースは小さくなっていきます。
明確に差をつける必要はありませんが、配置だけはしっかりイメージしておきましょう。
手順3:モノクロのままメリハリをつける
そして、実際のデータでレイアウトを作成していきます。
四角の図形を利用して先に作ったレイアウトを再現してみましょう。
今度はそれぞれのボックスに情報をテキスト化して入力していきます。
写真やイラストはとりあえず図形で代用し、文字の大きさを優先度に沿って変化させてください。
色はモノクロで構いません。
余白を確認しながら、全体のメリハリと見やすさを意識して組み立てましょう。
手順4:画像と色を設定する
最後にフォントも変化させて、チラシ全体を求める雰囲気に近づけていきます。
写真やイラストを配置して、背景や各フォントの色も決定しましょう。
ポイントは統一感を出すことです。
複数の色やフォントを使用するのではなく、2〜3種類にとどめた上でチラシ全体をデザインしましょう。
色の心理的効果を加味すると、さらに良いものが仕上がる可能性もあります。
フライヤー裏面をデザインする際のポイント
最後に、フライヤー裏面をデザインする際のポイントについて解説いたします。
押さえておきたい内容は以下のとおりです。
- 表やグラフを利用する
- 情報をブロック化する
- 視線の流れを意識する
- 単色刷りとカラー刷り
- アクセス情報は最後にするのが鉄則
- 裏面への誘導設計も重要
表やグラフを利用する
チラシの裏面には商品に関するデータを記載することも多いですが、その際に表やグラフを使うと、情報が視覚から入ってくるのでより分かりやすく伝わります。
文章だと長くなるような情報も省スペースで表せるので、アピールしたい有益な情報も紙面が許す限り掲載できるのがポイントです。
情報をブロック化する
レイアウトを決定する手順でも示したとおり、関連する情報はまとめてブロック化しておくことが大切です。
関連情報がバラバラに配置されていると、読み手を混乱させ読みにくさの上昇につながります。
情報はそれぞれブロック化し、適切に配置することが重要です。
視線の流れを意識する
レイアウトの基本に視線の流れを意識する考えがあります。
横書きの場合はZの文字、縦書きの場合はNの文字に視線が動くため、これに合わせて情報を配置する手法です。
情報を取得する順番を間違えるケースが少なくなり、スムーズに理解してもらえる効果が期待できます。
単色刷りとカラー刷り
単色刷りとカラー刷りの選択はフライヤーの持つ雰囲気に関係します。
単色刷りでは大衆イメージを連想させつつ、コストを抑えたフライヤーの作成が可能です。
カラー刷りではコストが増大しますが、フライヤーが与える印象や情報量などが格段にアップします。
フライヤーは高級で魅力的な販促ツールを指すことも多いので、基本的にはカラー刷りのほうがおすすめといえるでしょう。
アクセス情報は最後にするのが鉄則
アクセス情報が最後にあると、読み手にはスムーズに購買行動へと移れます。
ここでいう最後とは視線の流れにおける終点、つまり横書きなら右下、縦書きなら左下です。
この場所にアクセス情報を配置するのがフライヤー裏面におけるデザインの鉄則となります。
裏面への誘導設計も重要
フライヤー裏面が購買行動のきっかけになると理解していても、裏面への誘導設計がなければデザインの効果をうまく発揮できない場合があります。
まずは裏面に情報があること、そしてその内容が有益であることを読み手に知らせる設計が必要です。
「チラシの裏面にあるお得な情報をチェック」の一文だけでも効果があります。
裏面への誘導設計も重要ポイントですのでしっかり確認しておきましょう。
まとめ
フライヤーの裏面に記載された情報が、読み手を購買行動へ進ませる直接のきっかけとなります。
裏面も表面と同様、その役割をしっかり意識してデザインに臨むことが重要です。
フライヤーの裏面こそが真の購買契機と理解しつつ、ポイントを押さえたデザインの完成を目指しましょう。
「プリントアース」では、チラシやフライヤーなどの印刷だけではなく、デザイン制作サービスも行っています。
プリントアースのデザイン制作は専任デザイナーがしっかりサポートいたしますので、フライヤー裏面デザインにこだわりたいけど、どうしたらいいのかわからないという方は、これを機に「プリントアース」を利用してみてはいかがでしょうか。

