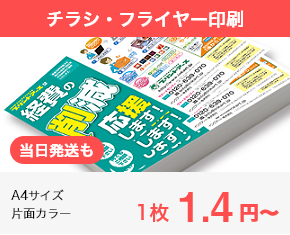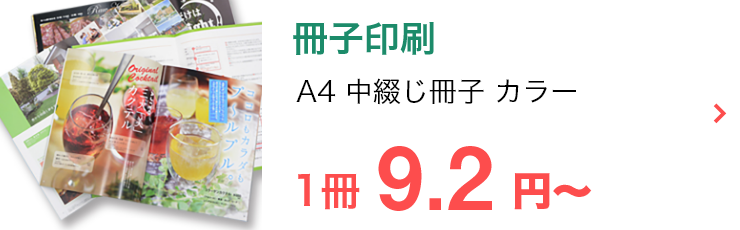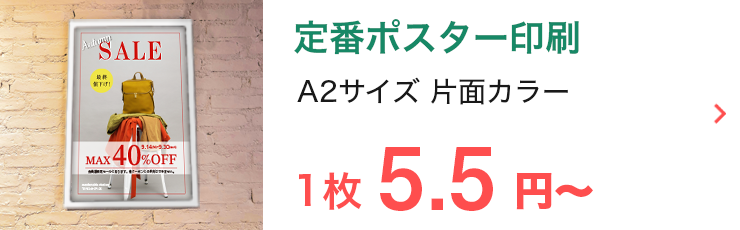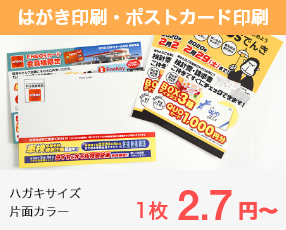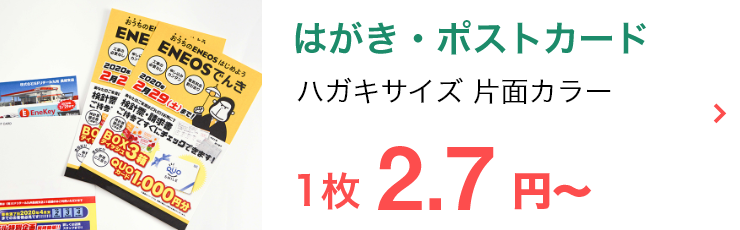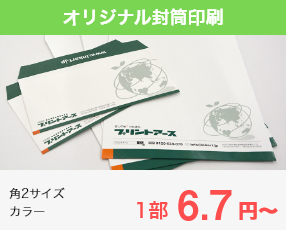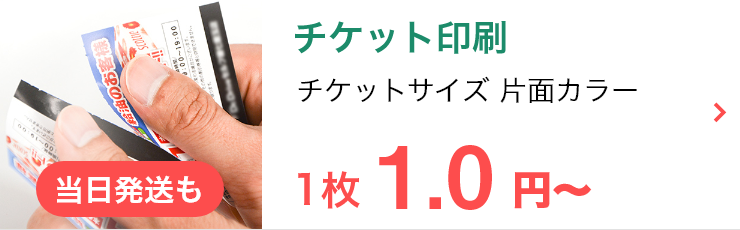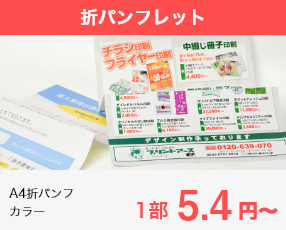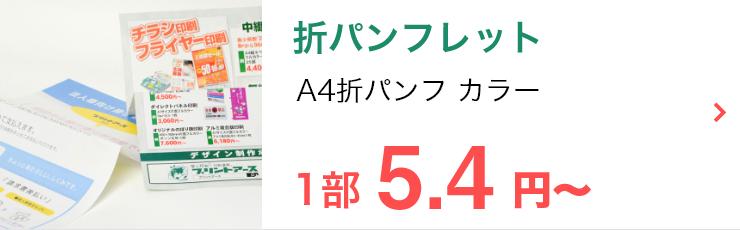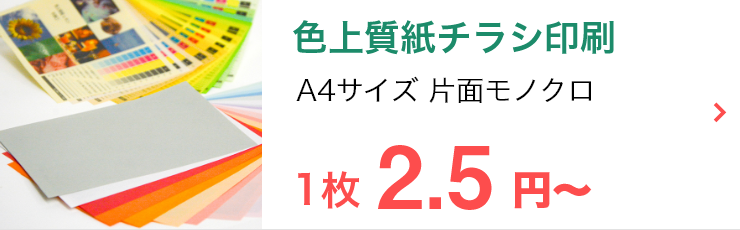冊子印刷は用途によって、使用するサイズが異なります。
ですが、どのサイズで作るべきかわからない方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、冊子印刷でよく使用されているサイズについて解説していきます。
サイズ選びのポイントや製本方法の選択についても解説しているので、ぜひ最後までご覧ください。
【 目次 】
印刷冊子に使用されているサイズとそれぞれの使用用途
それでは印刷冊子に使用されているサイズと、それぞれの使用用途について解説していきます。
A4:一般的な冊子サイズ
冊子として一般的なのはA4サイズです。
論文や参考書、カタログやアルバムなど、さまざまな冊子で使われているサイズです。
検索するとすぐに見つけられるサイズなので、完成形のイメージもしやすいでしょう。
掲載できる情報量と見やすさのバランスが優れているサイズといえます。
A5:教科書や専門書などのサイズ
教科書や専門書などのサイズはA5となります。
読み物に適したサイズで、学術誌や文芸誌としても見かけるサイズになります。
コンパクト性能が高く、運搬するのに困らない点がメリットです。
A6:文庫本サイズ
文庫本はA6サイズです。
携帯性が高いため、持ち運びする商品に使用されている傾向です。
小さいながら文字も書けるスペースがあるため、手帳としても使われているサイズになります。
コストを抑えて作成できる点が特長です。
B5:週刊誌や学習ノートのサイズ
週刊誌や学習ノートのサイズはB5となります。
読み物のサイズとして適している上に、イラストや大きめの見出しにも対応できるサイズで、持ち運び性能も高いサイズです。
B6:単行本サイズ
B6のサイズは持ちやすく見やすいサイズ感が特徴で、単行本としてよく見かけるサイズです。
文庫本として見かけるA6サイズより少し大きく、小説や同人誌にも使われています。
A判とB判の違い
冊子のサイズにはA判やB判の表示が使われていますが、それぞれの違いについてご存知でしょうか。
A判とB判の違いについても解説していきます。
A判
A判は国際的に普及している規格で、ドイツ発祥の工業規格です。
A0からA10まで、11種類の規格が存在しています。
B判
B判は国内のみで通用する規格で、江戸時代に端を発するものです。
B0からB10までと、こちらも11種類の規格で構成されています。
A判とB判の面積を比較すると、B判のほうが1.5倍大きなサイズとなります。
一般的な本のサイズ一覧
最後に一般的な本のサイズを一覧としてまとめておきます。
|
本の一例 |
サイズ(mm) |
名称 |
|
文庫 |
105×148 |
A6 |
|
新書本や漫画の単行本 |
103×182・105×173 |
新書判 |
|
単行本やコンビニコミック |
128×182 |
B6 |
|
コミック本 |
112×174 |
小B6 |
|
文芸書(単行本) |
127×188 |
四六判 |
|
学術書(単行本) |
152×218・152×227 |
菊判 |
|
週刊誌 |
182×257 |
B5 |
|
大型の雑誌 |
210×257 |
AB判 |
|
文芸雑誌や教科書 |
148×210 |
A5 |
|
画集 |
257×364 |
B4 |
|
絵本 |
182×206 |
重箱判 |
|
写真集 |
210×297 |
A4 |
|
洋書 |
110×178~152×229 |
ペーパーバック |
冊子印刷におけるサイズ選びのポイント
引き続き冊子印刷におけるサイズ選びのポイントについて解説していきます。
冊子印刷では、以下の3つを抑えておくと良いでしょう。
- 冊子の目的やターゲット
- デザインや情報量
- コスト
①冊子の目的やターゲット
サイズ選びの一つ目のポイントは、冊子の目的やターゲットによって、汎用性と携帯性のどちらが良いかを決定することです。
認知度を広げたいなら汎用性が高い一般的なサイズ、持ち運びを重視するならコンパクトなサイズがおすすめです。
②デザインや情報量
サイズ選びに関わる次のポイントは、デザインと情報量になります。
デザインとは写真やイラストの占める割合です。
デザインの割合が大きいほど、A4やB5といった大きめのサイズが最適となります。
情報量が指すのは文字の占める割合です。
イラストや写真よりも文字が多ければ、A5やB6のような小さいサイズがおすすめとなります。
③コスト
最後に注目したいのはコストです。
サイズが大きいほど、冊子印刷に必要なコストは上昇します。
コストを抑えたいなら、A5やB6のような小さいサイズを検討してみましょう。
コストについて考えるなら相場について知っておく必要があります。
冊子印刷の費用相場について詳しくはこちら
サイズだけではなく製本方法も冊子に合ったものを選択
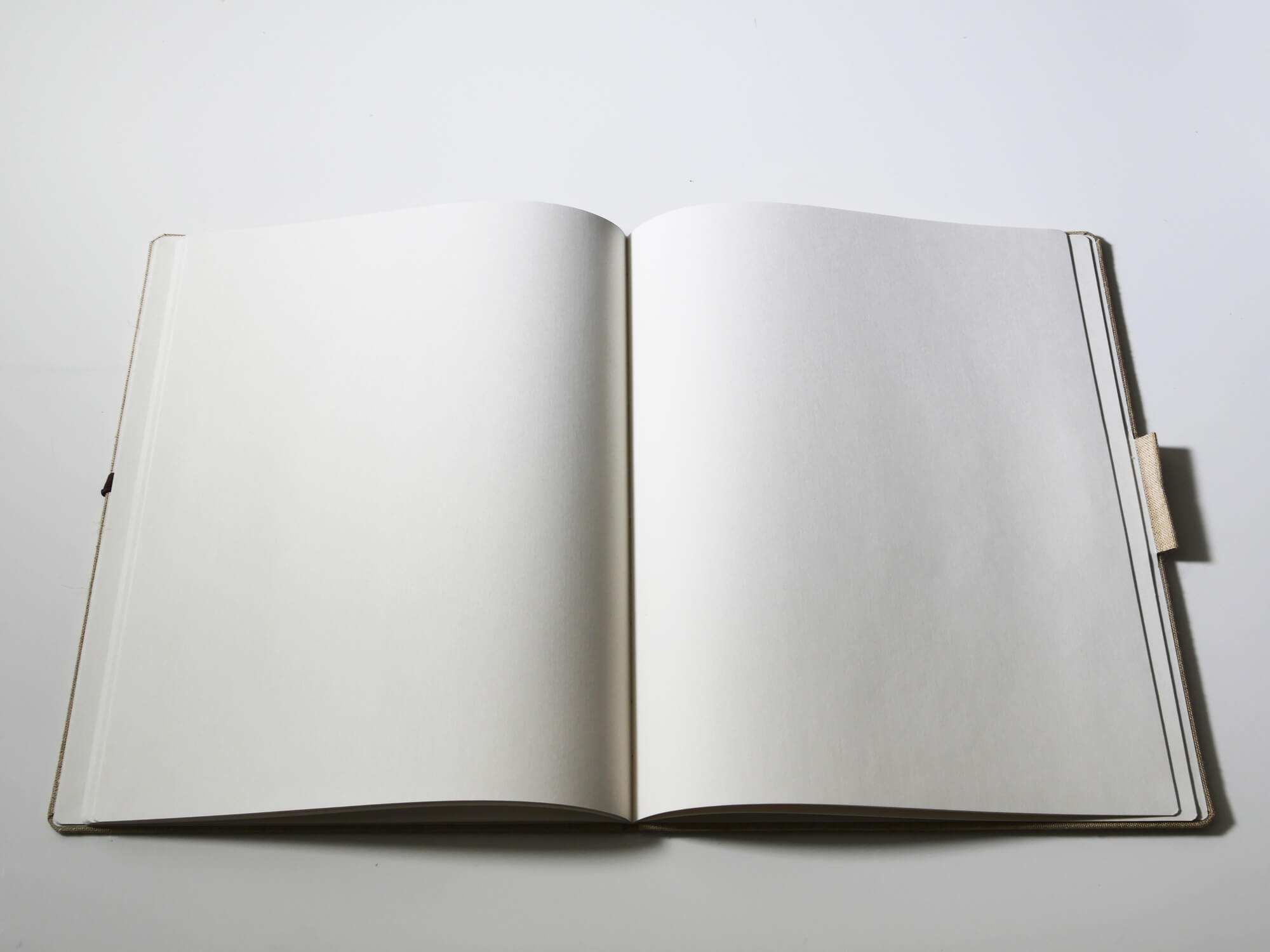
冊子の効果を高めるためにも、適したサイズの選択は重要なポイントですが、製本方法についてもしっかりと理解しておくことをおすすめします。
サイズと同様に製本方法にも適した種類があるので、目的の冊子に合った方法を選択することが必要です。
ページ数が少ないなら中綴じ製本
中綴じは2つ折りになったページの中央を、ステッチ(針金)を使って綴じる製本方法です。
見開きの部分を最大限開くことができ、ページ数が最大で64ページほどの少ない冊子に向いています。
したがってパンフレットや情報誌、カレンダーなどの媒体で使われる傾向です。
中綴じ製本について詳しくはこちら
ページ数が多いなら無線綴じ製本
中綴じがステッチを使うのに対して、無線綴じ製本は背表紙の部分を削ったあとにのり(接着剤)をつけて、最後に表紙ページで包んで綴じる方法です。
中綴じ製本では適さない、ページ数の多い冊子に向いています。
したがって大容量のカタログ、漫画の週刊誌、小説などに使われている傾向です。
無線綴じ製本について詳しくはこちら
エコや安全性を優先するならスクラム製本
エコや安全を優先したスクラム製本は、ステッチやのりを使わない製本方法です。
仕上がりの状態は中綴じ製本と似ていますが、針金を使わない点で安全性に勝り、コストも抑えられるという利点があります。
一方で、簡単にページがバラバラになってしまうというデメリットもある製本方法です。
まとめ
冊子印刷で使用されているサイズはA判とB判に分かれており、22種類の規格から本の種類に合わせて最適なサイズを選択する必要があります。
サイズ選びで注目すべきポイントは、冊子の目的やターゲット・デザインと情報量・コストの3つです。
冊子印刷のサイズに悩んでいる方や、サイズも含めて冊子全般の品質にこだわりたいという方は、プリントアースにお任せください。
印刷・製本のプロがお手伝いいたしますので、お気軽にお問い合わせください。